啓発事業における中学生による化学法則発見(鳥取大学)
化学コミュニケーション賞2024受賞者インタビュー
2025年8月掲載
鳥取大学工学部附属GSC研究センター 教授
片田 直伸 先生
鳥取大学附属中学校3年(現・鳥取県立鳥取西高校3年)
田村 隼央 さん

化学コミュニケーション賞の賞状を持つ片田先生(左)と、受賞記念の盾を持つ田村さん(右)
2024年の化学コミュニケーション賞を受賞した鳥取大学の片田直伸教授と鳥取西高校の田村隼央さんに、受賞の背景や活動内容についてお話を伺いました。鳥取大学では「目指せ!地球をつくる環境博士プログラム」という啓発事業を通じて、鳥取県や兵庫県の子どもたちに「環境」をキーワードとした一貫した教育や研究活動の機会を提供しています。今回のインタビューでは、同事業に参加された片田先生と田村さんに、受賞の経緯や教育・研究活動について詳しくお話しいただきました。
(インタビュー日:2025年8月5日)
化学コミュニケーション賞受賞の舞台裏
——化学コミュニケーション賞の受賞おめでとうございます。応募のきっかけを教えてください。
片田先生:私は触媒学会、日本ゼオライト学会、石油学会などに所属しており、いずれも日本化学連合に属する組織です。日本化学連合の活動にも関わっているため、「化学コミュニケーション賞」については運営側としてある程度把握していました。
ただ、正直なところ、これは化学教育業界向けの賞という認識があり、自分が該当するとは思っていませんでした。そんな中、ゼオライト研究でご活躍の横浜国立大学・窪田好浩先生から「片田さん、応募してみては?」とお声がけいただいたのです。
——それは意外な展開ですね。
片田先生:そうですね。鳥取大学では、中学生の田村さんがゼオライト研究の一翼を担い、高校生の時点で学術論文に名前を連ねたという素晴らしい事例がありました。この事例をゼオライト研究界だけでなく、より広く知っていただきたいと思っていたところでしたので、窪田先生の言葉に背中を押され応募しました。
——応募はどのように進められたのですか?
片田先生:田村さんが参加したJST(科学技術振興機構)のジュニアドクター育成事業「目指せ!地球をつくる環境博士プログラム」は、鳥取大学全体で取り組んだ事業です。学内で相談し、大学として応募することにしました。内容的には前例の少ない取り組みでしたので、応募書類は比較的自由に書かせていただきました。
——それぞれ、受賞の連絡を受けたとき、どのような感想を持たれましたか?
田村さん:片田先生から「受賞しました」と連絡をいただいたときは、「また何かに応募されたのかな?」と思いました(笑)。でも、話を聞いていくうちに自身が参加したプログラムだとわかり、また賞についても、「意外とすごい賞なのでは?」と気づき、嬉しかったです。
片田先生:鳥取大学としても初めての受賞でしたので、学長以下、非常に喜んでいました。工学部でもこうした賞をいただくのは滅多にないことですし、私自身も学内で表彰されました。
地域連携による探究型教育の実践とその成果
——啓発事業「目指せ!地球をつくる環境博士プログラム」について、ご説明いただけますか?
片田先生:このプログラムは、2017年にJSTの「ジュニアドクター育成塾」の一環として始まりました。鳥取大学は小規模な大学ですが、地域学部(注:地域における諸問題を解決すると共に地域の発展を担う人材の育成を目標としたユニークな学部)を有しており、その中に教育学の分野があり、附属学校も併設されています。加えて、工学・農学・医学など多様な分野が揃っていることから、特色ある取り組みが可能と判断され、採択されました。
工学部の「グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター(GSCセンター)」や、農学部の「国際乾燥地研究教育機構」など、地球環境に関係する部門が多く、また近隣の米子工業高等専門学校(米子高専)にもご協力いただき、「環境」をキーワードに一貫した教育・研究指導を行うことになりました。
——どのような方がこのプログラムに参加したのでしょうか?
片田先生:小学校5年生から中学校2年生までの児童・生徒が対象でした。鳥取県東部を中心に、兵庫県からの参加もあり、毎年30名ほどが参加していました。田村さんが参加されたのは、確かプログラムが始まって3年目だったと思います。
——具体的にはどのような活動が行われたのですか?
片田先生:参加者は1年目に「基礎コース」として、鳥取大学と米子高専の各研究室が設けたブースで講義形式の授業を行いました。1コマ約80分のプログラムを受講する形式です。夏休みや土日を中心に開催し、児童・生徒が参加しやすいよう工夫しました。
——科学教室のような形式ですね。
片田先生:ただし、大学としては単なる「科学教室」に終わらせないという方針がありました。授業の中では必ずディスカッションを行い、「答えが出ない問い」をテーマに議論を促しました。
——具体的には、どのような問いを設定されたのですか?
片田先生:私は「福島の原発事故で発生した放射性核種をゼオライトで除去できるか?」というテーマを設定しました。30人の参加者が3グループに分かれ、「できる」「できない」「できるかどうかわからない」という異なる結論を導き出しました。
——まさに科学的思考の訓練ですね。
片田先生:ええ。答えが出なくても、それが楽しいのです。確かにゼオライトを使って水から放射性物質を除去することは可能ですが、除去後のゼオライトには放射性物質が残るため、量的な観点から本当に除去できるのかという議論を行いました。
——その後、参加者は探究型の活動に移行されたのですね?
片田先生:はい。1年目は基礎的な内容を学び、2年目からは各自がテーマを選び、鳥取大学または米子高専で研究を進める形です。
このプログラムは数年間にわたり継続し、最終的には何百人もの「ジュニアドクター」を育成・輩出することができました。特徴的だったのは、「どのレベルの研究を行うか」を皆で決めた点です。私たちは「学会発表ができるレベルの研究を目指そう」と方針を定め、子ども向けの体験にとどまらず、本格的な研究に取り組んでもらうことを重視しました。
もちろん、すべてが順調に進んだわけではありませんが、私たちの研究グループは幸運にも成果が出て、新しい発見につながりました。
——小中学生に本格的な科学研究を指導する際、特に意識された点はありますか?
片田先生:「簡単に結果が出るけれど、意義のあるテーマ」を選ぶことでした。Langmuir誌に掲載された論文にも「実験は簡単です」と明記されています。溶液と固体を混ぜてろ過し、溶液中の成分を分析するだけの基本的なイオン交換の実験です。
——それでも、未解明な部分があるとは驚きです。
片田先生:はい。イオン交換の法則は非常に重要ですが、納得のいく原理がまだ十分に示されていない分野です。研究者は収益につながる応用研究に集中しがちで、基本原理の検証は後回しになっているのが現状です。
——そうしたテーマを中学生に提示されたのは、教育的にも挑戦だったのでは?
片田先生:大学生には提示しづらいテーマですが、田村さんのような意欲的な生徒にはぴったりでした。結果がすぐに出るけれど、そこから深く考える余地がある──そういうテーマを温めていたのです。
——JSTのプログラムは現在終了しているとのことですが、今後の展望は?
片田先生:JSTのサポートのもとで実施された時限的なプロジェクトでしたので、現在は新たな募集は行っていません。ただし、個別の受け皿としての仕組みは残っており、田村さんのように高校での課題探究に大学が連携するケースは続いています。
田村さん:私が通っている鳥取西高校はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されていて、その一環で「課題研究」という授業があります。私たちは3人でチームを組んでおり、研究内容が片田先生と同じ学科の赤松先生(※)の専門であるキチンやキトサンの分野と近いため、赤松先生の研究室にも何度かお邪魔して、さまざまなご指導をいただきました。
※赤松先生のCAS SciFinderユーザーインタビューの記事
https://www.jaici.or.jp/solutions/interview/cas-scifinder/sf-case05/
——これまでの取り組みには、確かな成果があったと感じられますか?
片田先生:はい。鳥取大学としては、研究者と中等教育に携わる教育学の専門家が連携し、意欲的な生徒が育ったことは、社会的に大きな意義があったと感じています。受賞内容にもあるように、有形・無形の影響が周囲に広がっており、科学への関心を引き起こすことができたと感じています。
ゼオライト研究に挑んだ過程とその学び
——田村さん、「環境博士プログラム」に参加されたきっかけを教えていただけますか?
田村さん:はい。中学校の理科の先生が、ある日「ジュニアドクター育成塾」のチラシを配ってくださったんです。それを見たとき、「なんだか面白そうだな」と思いました。こんな取り組みがあるんだと興味が湧いて、「自分もやってみたい」と思い、家族と相談して参加を決めました。
——鳥取大学附属中学校に通われていたとのことですが、大学とはすぐ隣なのですね?
田村さん:はい、本当に隣にあります。理科室にある顕微鏡も鳥取大学から譲り受けたもので、そうしたつながりがあったからこそ、自然と密接な関係が築かれていたのだと思います。
——実際に参加してみて、印象に残っている講義やイベントはありましたか?
田村さん:はい。最初の基礎講座で「砂漠がどのようにできるのか」というメカニズムを学んだのがとても面白く、印象に残っています。鳥取砂丘もありますし、乾燥地研究が盛んな地域なので、非常に身近に感じました。
片田先生:乾燥地に関するテーマは、鳥取ならではの特色ですね。
——その後、ゼオライトの研究に進まれたのは、どのような理由からですか?
田村さん:講義をすべて受けた後、探究活動に入る段階でいくつかのテーマから選ぶことになったのですが、その中で一番心を惹かれたのがゼオライトでした。砂漠の話も面白かったのですが、それ以上にゼオライトに「これだ!」と強く惹かれました。
片田先生:私は「このテーマは難しいから、誰も来ないだろう」と思っていたのですが、田村さんともう一人の生徒さんが参加してくれました。
——片田先生の講義や研究室の雰囲気も影響したのでしょうか?
田村さん:それもあると思います。研究室に入ってからは、ゼオライトのイオン交換能(注:ゼオライトの結晶構造内のナトリウムイオンを、水溶液中のセシウムイオンと入れ替える能力)に着目したテーマに取り組みました。
片田先生:「福島第一原発事故に伴う処理水の浄化にゼオライトが使われている」という話から始めました。実際に水中のセシウムの成分が消える様子を見てもらいながら、実験に取り組んでもらいました。
——セシウムを使った実験とのことですが、放射性物質を扱ったということでしょうか?
片田先生:いいえ、放射性を持たないセシウムの化合物(硝酸セシウム)を使用しました。ゼオライトの種類によってセシウムの除去能力は異なるのですが、ゼオライトがセシウムを除去する仕組みは単なるイオン交換であり、放射性とは関係ありません。ナトリウムとセシウムのイオン交換のメカニズムを調べることが目的であれば、放射性を持たないセシウムでも十分にシミュレーションが可能です。
——実験の計画は田村さんたちが立てたのでしょうか?
田村さん:はい。どのゼオライトを何グラム使うか、硝酸セシウムをどれだけ入れるかなど、自分たちで決めて実施しました。
——結果はいかがでしたか?
片田先生:研究の1年目は結果がバラバラで、収拾がつかない状態でした。ナトリウムとセシウムのどちらを好むかはゼオライトによって千差万別で、そこに法則性がないことから探究が始まりました。そこで2年目はLangmuir式に沿ったプロットができるような実験をしてもらい、解析を行いました。
——田村さん、研究を始めたときの気持ちはいかがでしたか?
田村さん:最初は答えが簡単に出たのですが、そこからどう進めていくかが難しくて、「これでいいのかな?」という漠然とした不安がありました。学校の実験と違って、ゴールが示されていないんです。
——平衡定数などの知識は、まだ習っていない時期ですよね?
田村さん:はい。片田教授の講義を受けたり、自分でも調べたりして勉強しました。高校に入ってから「あのときのあのことだったんだな」と納得しました。
片田先生:最初は濃度の概念やモルなど、基本的なところから教える必要がありました。なるべく簡単に伝えようとしましたが、難しかったですね。
——実験を通じて、科学の面白さを感じた瞬間はありましたか?
田村さん:はい、ずっと面白かったです。「実験できるんだ!」と思って、意気揚々と大学に通っていました。また、大学院生のメンターの方が丁寧に教えてくださって、本当に助かりました。
——学校生活への影響はありませんでしたか?
田村さん:ほとんどありませんでした。中学校の先生にも活動内容を伝えていたので、見守っていただいていました。
——高校受験との両立も大変だったと思いますが?
片田先生:中学2年・3年の時期でしたので、私も心配して何度も確認しました。でも、田村さんは「大丈夫です」と言って、実際に鳥取西高校に合格しましたね。
田村さん:本当にちゃんと大丈夫だったので、今、鳥取西高校に通っています。
——県内トップクラスの高校ですね。ところで、研究活動の中で、印象に残っているやり取りはありますか?
田村さん:ゼオライトのことは全く知らなかったので、知識を持っている方と関われるのがすごく楽しかったです。話を聞くだけでも面白くて、尊敬できる先生ばかりでした。
片田先生:田村さんは高校に入ってからも、家が大学に近かったこともあり、時々挨拶がてら研究室に遊びに来てくれました。ある時、たまたま共同研究で研究室に来ていた東京大学のスペイン人の助教が、田村さんを東大へリクルートしようとしていたこともありました。「田村さん、東京に来て」と英語で熱心に誘っていましたね(笑)。
田村さん:ありがたいことでしたが、私は人混みが苦手で……。英語で話しかけられて、なんとか聞き取れたのですが、返すのが難しかったです。
中学生研究者の挑戦と成長
——田村さんが日本化学会春季年会で研究発表されたのは、片田先生の提案だったのですか?
片田先生:はい、私が「せっかくだから、学会で発表してみようよ」と勧めました(笑)。
——中学生が日本化学会で研究発表するというのは、非常に珍しいことですね。
片田先生:日本化学会事務局に確認したところ、「中学生による学会本体での研究発表は史上初ではないか」という見解をいただきました。
——中学3年というと、ちょうど高校受験と重なる時期ですが、準備は大変だったのでは?
片田先生:日程はしっかり確認し、受験スケジュールに支障が出ないよう配慮しました。田村さんの成績は比較的余裕がありましたので、問題なく進めることができました。
——ポスターセッションのポスターも、ご自身で作成されたのですか?
田村さん:はい、自分で作成しました。発表準備も含めて、非常に有意義な時間でした。高校に入ってからポスター発表の機会が増えましたが、この経験がその基礎になっています。
——学会での初めての発表はいかがでしたか?
田村さん:とても緊張しました。自分が思っていた以上に独特の空気感があり、かなり緊張しました。正直、何を話したかは、今ではほとんど覚えていません(笑)。
片田先生:日本化学会会長の菅先生がポスター発表の場に来てくださり、議論や写真撮影までしていただきました。
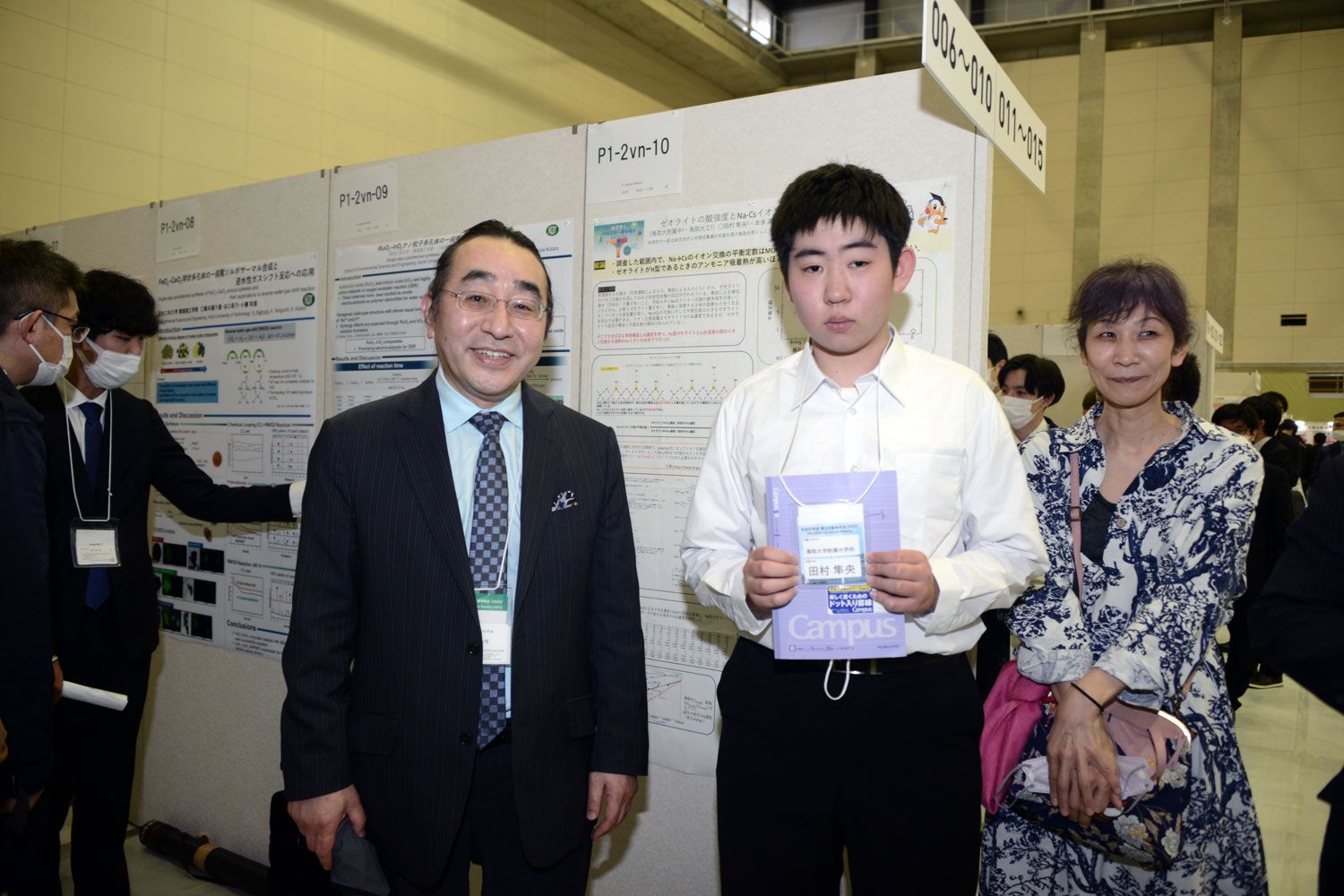
日本化学会会長の菅裕明先生(左)と田村さん
——片田先生も、田村さんのプレゼンの様子をご覧になっていたのですね?
片田先生:はい、ずっと横で見守っていました。見た感じでは、それほど緊張しているようには見えませんでした。話題性のある発表だったため、絶え間なく人が訪れていましたが、すべての質問にしっかりと答えていました。しかも、わかりやすい言葉で堂々と説明していました。
——先生の目から見て、発表の出来はいかがでしたか?
片田先生:もし彼が大学院生だったとしたら、60点くらいですね。
田村さん:絶妙な数字ですね(笑)。
片田先生:学会発表で100点満点はなかなかありませんからね。ただ、準備段階で非常に驚いたのは、田村さんが予稿原稿やポスター原稿など、私が依頼するとすぐに対応してくれたことです。大学院生でも、なかなかそうはいきません。
田村さん:私の信条として、連絡はなるべく早く確認し、できるだけ迅速に返信するよう心がけています。私は行動に移すのが早いタイプではないので、少し早めに始めておくことで、結果的にみんなと同じペースで進められるように心がけています。
片田先生:それは非常に素晴らしい姿勢です。大学院生だとすれば、150点くらいあげたいですね。
——素晴らしい心がけですね。しかもこの時期はコロナ禍だったのですよね?
片田先生:はい。連絡は主にZoomやメールを使っていました。やり取りはほぼオンライン経由で、実験に来るのは最低限という形でした。Zoomでの会話も多く、発表の頃にはすっかり慣れていました。
——メールが送られてきたらすぐ返すというのは、研究者としても非常に重要な姿勢ですね。
片田先生:ええ。田村さんが今後大学に進学して研究室に入ったとき、私が教えた中で最も役に立つのは、こうした姿勢ではないかと思います。
——その後、Langmuir誌に論文1)が掲載されました。自分の名前が国際的な学術誌に載ったことについて、どのように感じましたか?
1) Naonobu Katada*, Hayato Tamura, Takuya Matsuda, Yuya Kawatani, Yu Moriwaki, Manami Matsuo and Ryota Kato, “Correlation between Na-Cs Ion Exchange Property in the Alkaline Form and Acid Strength in the Proton Form of Zeolite”, Langmuir, 40, (37), 19324-19331 (2024).
https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c00801
田村さん:正直、最初は少し他人事のように感じていました。最後の段階はほとんど教授たちが進めていたので、私は詰めの部分には関わっていませんでした。だから、「報告の一部なんだろうな」と思っていたのですが、よくよく見てみると自分の名前が載っていたので驚きました。とても嬉しかったです。
片田先生:田村さんは共著者ですし、他の学生や先ほど話に出たメンターの学生も名を連ねています。原稿は私が執筆しましたが、提出前には全員に確認を取り、了承を得ています。田村さんにも毎回メールで連絡していました。
——高校生の段階でそうした経験ができるのは、本当に貴重ですね。今後の糧になると思います。
片田先生:繰り返しになりますが、田村さんの研究姿勢や能力で特に印象に残っているのは「反応の速さ」です。中学生ですから、難しい課題を出して期限を設けるのは難しいかと思っていたのですが、すぐに返答があったのです。
——「面白そう」「やってみたい」と言うだけでなく、実際にすぐ行動に移されたのですね。
片田先生:そうなんです。その姿勢に、強い意欲を感じました。研究室のメンバーの中でも、最もやる気があったと思います。大学生にもそう伝えていました。もちろん、内容的には難しくて分からないことも多かったと思いますが、Zoomで講義を行いながら説明する中で、分からない点は率直に質問してくれました。その貪欲な知識の吸収力には、本当に感心しました。
——なるほど。田村さんの姿勢が、研究者としての素養を育んでいたのですね。ところで、地元の日本海新聞にも記事が掲載されたそうですが。
片田先生:Langmuir誌に論文が採択された際、大学からプレスリリースを出しました。その際、私ではなく田村さんのもとに直接、日本海新聞から取材の申し込みがあり、記事が掲載されました。
——高校では話題になりましたか?
田村さん:意外とそうでもありませんでした。私自身、友人にあまりそういう話をしないので。ただ、校長先生や教頭先生からはお褒めの言葉をいただきました。
——研究を学会や論文で発表し、その内容が新聞にも取り上げられる──まさに化学コミュニケーションの理想的な形ですね。
啓発活動の意義と未来へのまなざし
——今回の啓発事業を通じて、片田先生は多くの小中学生と接し、研究や教育活動を行われましたが、この取り組みの成果や意義について、どのようにお考えですか?
片田先生:私が本業の研究活動を通じて強く実感しているのは、人類の課題を解決するためには、より多くの人に化学を理解してもらう必要があるということです。たとえば、カーボンニュートラル社会の実現には、相当な知識が求められます。良い解決策は、化学の理解なしには生まれません。
——確かに、環境問題の解決には化学的な知識が不可欠ですね。
片田先生:そうですね。今、私はまさにその課題に直面しており、強く感じています。化学で生計を立てる人、つまり化学系の企業に就職する人だけでなく、もっと幅広い層に興味を持ってもらう必要があります。化学業界としても、戦略的に取り組むべき課題だと考えています。
——これまでの「化学を目指す人を増やす」という目標とは、少し違う方向性ですね。
片田先生:ええ。これまでは漠然と「理系に進む人を増やそう」といった目標でしたが、今はそれとは桁違いの関心を引き出す必要があると感じています。どうすればそれが実現できるかは、まだ明確な答えはありません。だからこそ、こうした啓発活動も含めて、試行錯誤が必要だと思っています。
——啓発活動そのものが、研究課題になっているということですね。
片田先生:はい。私は、こうした活動そのものが新しい研究課題だと捉えています。ありきたりな答えならいろいろ語ることはできますが、それで市民の皆さんの知識が世界的に向上したかというと、なかなかそうは言えません。これは、答えのない共通の悩みだと思います。
——確かに、化学をどう伝えるかは、教育だけでなく社会全体の課題ですね。
片田先生:そうですね。ただ、私たちはそういう時代に差し掛かっていると感じています。毎日暑かったり、海面が本当に上昇してきたりしている。それはある意味、チャンスでもあります。啓発活動をもっと広げるべき時期なのかもしれません。今は、ボールを投げれば誰かが打ち返してくれる──そんな手応えを感じています。
——ありがとうございます。田村さんは現在高校3年生とのことですが、今後どのような進路を考えていますか?
田村さん:そうですね、将来のことはまだはっきりとは決まっていませんが、今一番近い目標は大学進学です。私は鳥取大学工学部化学バイオ系学科、片田先生がおられる学科への進学を希望しています。
——ゼオライト研究も続けられるかもしれませんね。
田村さん:はい。もしかしたらゼオライト以外にも面白そうな分野が見つかるかもしれませんが、今のところは化学分野に進みたいと思っています。ゼオライトについても、また取り組んでみたいという気持ちはあります。
片田先生:実は、このプロジェクト全体を通じて、これが一番の成果だと思っています。
——田村さんのような人材が育ったことですね。
片田先生:そうです。これだけモチベーションが高く、周囲に良い影響を与えてくれる人が育ってくれたことが、何よりの成果です。
——本日は、いろいろと貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
田村さんの研究姿勢と反応の速さ、それを支える片田先生の導きは、理想的な学びのかたちでした。中学生が大学で研究に挑み、学会発表を経て地元紙に取り上げられるまでの過程は、まさに化学コミュニケーションの実践です。「周囲に良い影響を与える人が育ったことが何よりの成果」という片田先生の言葉は、この啓発活動の本質を物語っています。科学を社会に届ける力が未来を育てることを、私たちは確かに感じました。
受賞者紹介

片田 直伸(かただ なおのぶ)先生
鳥取大学工学部化学バイオ系学科教授。1990年名古屋大学大学院工学研究科応用化学および合成化学専攻修士課程修了。1996年、名古屋大学より博士(工学)を取得。1990年より株式会社日本触媒に勤務。1992年より鳥取大学工学部に着任し、助手、講師、助教授、准教授を経て、2011年より教授。現在、鳥取大学工学部附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター長を務める。専門は固体触媒化学、特に固体酸触媒の原理と応用。国際ゼオライト学会Projectリーダー、日本ゼオライト学会副会長、石油学会副会長などを歴任。日本学術振興会専門研究員(2020–2024)、Aramco社研究所顧問委員会委員(2022-2024)も務めた。2003年に触媒学会奨励賞、2004年に石油学会奨励賞などを受賞。

田村 隼央(たむら はやと)さん
鳥取県立鳥取西高等学校在学中(2025年現在、高校3年生)。鳥取大学附属中学校出身。中学時代にジュニアドクター育成塾「めざせ!地球を救う環境博士」に参加し、鳥取大学工学部片田直伸教授の指導のもと、固体触媒化学の研究に従事。研究テーマは、放射性物質の固定化に有効な固体「ゼオライト」のイオン交換能に関するものであり、従来の「空間サイズによる選択性」という定説を覆し、「ゼオライトの化学特性が選択性に影響する」ことを初めて示した。この成果は、日本ゼオライト学会誌『ゼオライト』および米国化学会の学術誌『Langmuir』に掲載され、国内外で高く評価された。また、2023年3月には、日本化学会第103春季年会にてポスター発表を行い、中学生として通常セッションで発表した初の事例として注目を集めた。
